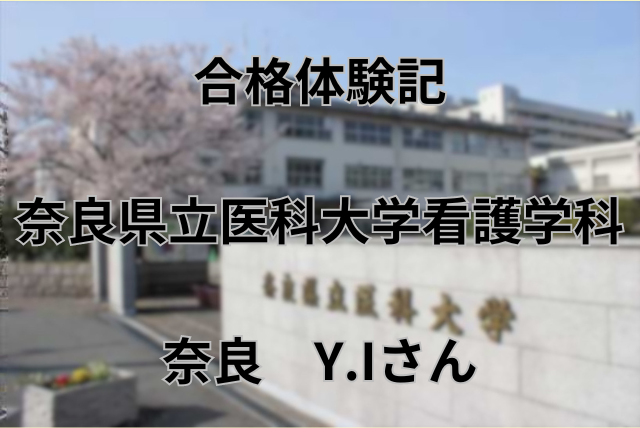こんにちは。あんちもです。
前回は看護学科の小論文の特徴と対策の基本姿勢についてお伝えしました。今回は、看護小論文で効果的に使える「医療・看護系キーワード」について解説します。適切な専門用語を使いこなすことは、あなたの小論文に説得力と専門性を与え、看護学科の入試で高評価を得るための重要なスキルです。
医療・看護系キーワードの重要性
看護学科の入試において、適切な医療・看護系のキーワードを使用することには、以下のような意義があります:
- 志望意欲の証明:基本的な看護用語を理解していることは、看護への関心の高さを示します
- 専門的思考の表現:専門用語を適切に使うことで、医療者としての視点や思考が表現できます
- 論述の効率化:専門用語を使うことで、複雑な概念を簡潔に伝えることができます
- 入学後の学習への準備:入学前から基礎知識を身につけることで、専門教育へのスムーズな移行が期待できます
ただし、注意すべき点もあります。単に専門用語を散りばめるだけでは効果はなく、むしろ誤用は逆効果となります。専門用語は「自分の考えを正確に伝えるための道具」と考え、適切な理解のもとで使用することが大切です。
必ず押さえておきたい基本概念
看護小論文で頻出する基本的な概念とキーワードを、カテゴリー別に紹介します。これらの概念を正確に理解し、適切に使用できるようになりましょう。
1. 看護の基本理念に関するキーワード
- ケア(Care):看護の本質的な概念。単なる「世話」ではなく、対象者の健康と幸福のための総合的な支援を意味します。
- QOL(Quality of Life、生活の質):病気の治療だけでなく、患者の生活の質を重視する考え方。「どう生きるか」という質的側面に焦点を当てます。
- ホリスティックケア(全人的ケア):人間を身体・精神・社会的側面を持つ統合体として捉え、総合的にケアする考え方です。
- エンパワメント:患者自身が自分の健康や生活をコントロールする力を高めるプロセスを指します。
- アドボカシー(権利擁護):患者の権利や意思を守り、代弁する看護師の重要な役割です。
小論文での活用例:
現代の看護において求められるのは、単に疾患を治すだけでなく、患者のQOLを高める視点である。特に高齢者医療では、最先端の治療技術だけでなく、その人らしい生活を支えるホリスティックケアの実践が重要となる。
2. 看護実践に関するキーワード
- 看護過程:アセスメント、診断、計画、実施、評価という一連の問題解決プロセスです。
- フィジカルアセスメント:視診・触診・打診・聴診などの技術を用いた身体状態の評価です。
- インフォームド・コンセント:医療行為について十分な説明を受けた上での患者の同意です。
- リスクマネジメント:医療事故を予防し、安全な医療を提供するための組織的取り組みです。
- POS(Problem Oriented System):問題志向型システム。患者の問題に焦点を当てた記録・対応法です。
小論文での活用例:
看護師は日々のケアの中で、常に看護過程に基づいた実践を行っている。例えば、高齢患者の転倒リスクについてアセスメントを行い、問題点を明確化した上で予防策を計画・実施し、その効果を評価するというプロセスを踏むことで、科学的な看護を提供している。
3. 医療・福祉制度に関するキーワード
- 地域包括ケアシステム:高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制です。
- 在宅医療:病院ではなく自宅で受ける医療。訪問看護はその重要な一翼を担います。
- 多職種連携(チーム医療):医師、看護師、薬剤師、理学療法士など多様な専門職が協働して医療を提供する体制です。
- 医療の質評価:医療サービスの質を客観的に評価し、改善するための取り組みです。
- 医療資源の適正配分:限られた医療資源を公平かつ効率的に配分する考え方です。
小論文での活用例:
超高齢社会の日本では、地域包括ケアシステムの構築が急務となっている。このシステムの中で看護師には、病院と在宅をつなぐ役割や多職種連携のコーディネーターとしての役割が期待されている。
4. 医療倫理に関するキーワード
- 自律尊重:患者の自己決定権を尊重する原則です。
- 無危害:患者に害を与えないという原則です。
- 善行:患者の利益を最大化するという原則です。
- 公正:医療資源を公平に分配するという原則です。
- インフォームド・コンセント:十分な情報提供に基づく同意です。
- 守秘義務:患者情報の秘密を守る義務です。
小論文での活用例:
終末期医療における意思決定では、患者の自律尊重と善行原則が時に対立することがある。例えば、医学的に効果が期待できない治療を患者が希望する場合、看護師は患者の意思を尊重しつつも、最善の利益とは何かを多角的に考える必要がある。
5. 現代医療の課題に関するキーワード
- 医療の高度化・専門化:医療技術の進歩による治療の高度化・専門分化です。
- 少子高齢化:人口構造の変化による医療ニーズの変化を指します。
- 医療格差:地域や経済状況による医療アクセスの不平等です。
- 医療安全:医療事故を防ぎ、安全な医療を提供する取り組みです。
- メンタルヘルス:心の健康に関する問題と対策です。
小論文での活用例:
医療の高度化・専門化が進む一方で、患者の全体像を捉える視点が失われる危険性も指摘されている。このような状況において、看護師には専門的知識を持ちながらも、常に患者を一人の人間として全体的に捉えるホリスティックな視点が求められる。
キーワードの効果的な活用法
看護系キーワードを小論文で効果的に活用するためのポイントを紹介します。
1. 文脈に合った適切な使用
専門用語は、その概念が必要な文脈で使うことが重要です。無理に専門用語を詰め込むと、かえって読みにくい文章になります。
不適切な例:
私は看護師になって、インフォームド・コンセント、アドボカシー、エンパワメント、ホリスティックケアを実践したいです。
改善例:
私は看護師として、患者さんの意思決定を支える(インフォームド・コンセント)とともに、時に患者の権利を守る代弁者(アドボカシー)となり、自らの力で健康を獲得する力を引き出す(エンパワメント)支援をしたいと考えています。そのためには、患者さんを身体面だけでなく、心理面・社会面を含めた全人的な存在(ホリスティック)として捉える視点が不可欠です。
2. 正確な理解に基づく使用
専門用語の意味を正確に理解し、適切に使用することが重要です。曖昧な理解での使用は避けましょう。
誤用例:
患者のQOLを高めるために、看護師はフィジカルアセスメントを活用して心のケアをすることが大切だ。
正しい例:
患者のQOLを高めるためには、看護師はフィジカルアセスメントによる身体状態の正確な評価とともに、精神的・社会的側面にも目を向けた全人的なケアを提供することが重要である。
3. 具体例と結びつけた使用
抽象的な概念を具体例と結びつけることで、理解が深まり説得力が増します。
抽象的な例:
地域包括ケアシステムは高齢社会において重要である。
具体例と結びつけた例:
一人暮らしの認知症高齢者が増加する中、医療・介護・生活支援などが連携した地域包括ケアシステムの構築は、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を続けるために不可欠である。例えば、訪問看護師による定期的な健康管理、デイサービスでの社会交流、見守りボランティアによる生活支援など、多様なサービスを組み合わせることで、施設入所を遅らせることができる。
4. 自分の言葉で噛み砕いて説明
専門用語を使った後に、自分の言葉で補足説明を加えると、理解度が伝わります。
専門用語のみの例:
看護師にはアドボカシーの役割が重要である。
噛み砕いた例:
看護師にはアドボカシー、つまり患者の権利や意思を守り、時には代弁者となる役割が重要である。例えば、意識の低下した患者に対して医療従事者が事務的に処置を行おうとする場面では、「この方はどのような思いでこの治療を受けているのか」という視点から患者の尊厳を守る働きかけをすることが求められる。
実践練習:キーワードを活用した小論文例
以下のテーマで専門用語を適切に使った小論文の例を紹介します。
テーマ:「高齢化社会における看護師の役割について、あなたの考えを400字程度で述べなさい」
解答例:
高齢化社会において看護師に求められる役割は、疾病の治療支援にとどまらず、高齢者のQOL向上を目指したホリスティックケアの実践者となることである。高齢者は複数の慢性疾患を抱え、身体機能の低下とともに社会的孤立などの問題も抱えやすい。そのため看護師には、フィジカルアセスメントによる身体状態の評価だけでなく、精神的・社会的側面も含めた総合的なアセスメント能力が求められる。 特に地域包括ケアシステムの進展に伴い、看護師には病院と在宅をつなぐ役割や多職種連携のコーディネーターとしての機能も期待されている。例えば、退院支援においては、患者の生活背景を考慮した退院計画の立案や、地域の医療・介護資源を活用した継続的なケア体制の構築が重要となる。 これからの看護師には、高齢者の自律性を尊重しながら、その人がその人らしく生きることを支えるエンパワメントの視点に立ったケアが不可欠である。
看護系キーワードを学ぶ方法
看護系のキーワードを効果的に学び、理解を深めるための方法を紹介します。
1. 看護学の入門書を読む
看護学の基本的な教科書や入門書を読むことで、基礎的な概念や用語を学ぶことができます。特に「看護学概論」「基礎看護学」などの分野の本は、看護の基本理念や考え方を学ぶのに適しています。
2. 看護・医療系の雑誌や新聞記事を読む
「看護」「医学のあゆみ」などの専門誌や、新聞の医療・健康欄を定期的に読むことで、最新の医療・看護の動向や課題について学ぶことができます。
3. 看護系大学のオープンキャンパスや公開講座に参加する
看護系大学のオープンキャンパスや公開講座では、看護の専門家から直接話を聞く機会があります。積極的に質問することで理解を深めましょう。
4. 医療ドキュメンタリー番組を視聴する
NHKスペシャルやプロフェッショナル仕事の流儀などの医療・看護を扱った番組では、現場の実態や看護師の思考プロセスを学ぶことができます。
5. 小論文の過去問を分析する
志望校の過去の小論文問題や模範解答を分析し、どのような専門用語が使われているかを研究することも効果的です。
次回予告と今回のまとめ
今回は看護小論文で使える医療・看護系キーワードについて解説しました。適切な専門用語を使いこなすことで、あなたの小論文の説得力と専門性が高まります。ただし、単に用語を羅列するのではなく、正確な理解に基づいて、文脈に合わせて適切に使用することが重要です。
次回は「患者の視点と医療者の視点」について解説します。看護小論文では、複数の視点から問題を考察することが求められます。患者、家族、医療者など、異なる立場からの視点をどのように小論文に取り入れ、多角的な考察を展開するかについて詳しく解説していきます。
皆さんの看護小論文学習が実り多きものになることを願っています。