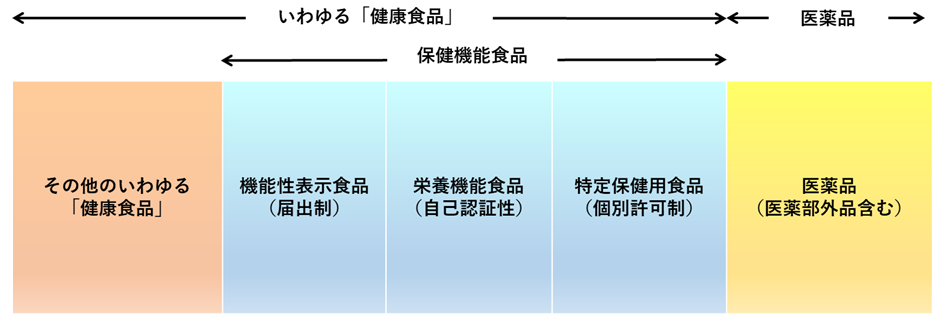こんにちは。あんちもです。
前回は「チーム医療の視点からの考察」について解説しました。今回は「看護の専門性と社会貢献」をテーマに、看護という職業がもつ独自の専門性とは何か、そしてその専門性を活かして社会にどのように貢献できるのかについて考えていきましょう。
看護学科の入試、特に小論文や面接では「看護師として何を大切にしたいか」「看護師として社会にどう貢献したいか」といった問いが頻出です。こうした問いに答えるためには、看護の専門性についての理解を深めることが不可欠です。また、高齢化や医療の変化に伴い、看護師の役割は病院内だけでなく地域社会へと広がりをみせています。看護師として社会にどのように貢献できるのかという視点も持っておきましょう。
看護の専門性とは何か
「看護の専門性とは何か」という問いは、一見シンプルですが、実は深く考えると奥が深いものです。ここでは、いくつかの視点から看護の専門性について考えてみましょう。
1. 生活者の視点でのケア
看護の最大の特徴は、「生活者」としての人間を対象としたケアを行うことです。医師が主に「疾患」に焦点を当てるのに対し、看護師は「病を持つ人」全体に焦点を当てます。つまり、単に症状や検査データを見るだけでなく、その人の生活習慣、価値観、家族関係、社会的背景まで含めて総合的に捉えるのが看護の視点です。
例えば: 同じ糖尿病の患者さんでも、独居の高齢者、小さな子どもを育てる母親、長距離トラックの運転手など、生活背景によって必要なケアや指導内容は大きく異なります。看護師はこうした個別性を大切にしながらケアを提供します。
2. 「生きる」を支える実践知
看護の専門性の中核には、人間の「生きる」を支える実践的な知識や技術があります。これは単なる医学的知識だけでなく、人間の発達段階や心理、環境との相互作用など、幅広い知識を統合したものです。
例えば: 呼吸困難のある患者さんに対して、医学的知識(呼吸生理学など)に基づいて状態を観察しながら、その人が最も楽に呼吸できる姿勢の工夫や、不安を和らげるための声かけなど、総合的なケアを提供します。
3. 予防的視点と健康増進
看護の専門性として、すでに起こった問題への対応だけでなく、「予防」と「健康増進」の視点があります。健康障害が起こる前に予防的に関わったり、その人が持つ健康な側面を強化したりするアプローチです。
例えば: 入院患者さんの場合、現在の疾患の治療をサポートするだけでなく、長期の臥床による褥瘡(床ずれ)や廃用症候群を予防するケア、退院後の生活を見据えた健康教育なども看護師の重要な役割です。
4. 継続的な関わりと変化の見守り
看護の専門性として、24時間365日の継続的な関わりがあります。短時間の診察や処置ではなく、継続的に患者さんと関わることで見えてくる変化や回復のプロセスを見守り、支援することが看護の重要な役割です。
例えば: 終末期の患者さんに対して、身体的な症状の変化を捉えながら、心理的な変化や家族の受容プロセスにも寄り添い、その時々に必要なケアを提供します。
5. 代弁者(アドボケイト)としての役割
看護師は、自分の意思を十分に表明できない患者さんの代弁者(アドボケイト)としての役割も担っています。患者さんの権利や尊厳を守り、患者さん中心の医療が実現されるよう働きかけるのも専門性の一つです。
例えば: 認知症の高齢者や意識のない患者さんの場合、そのしぐさや表情から思いを汲み取り、医療チームにその患者さんの意向や必要性を伝える役割を担います。
看護師による社会貢献の形
次に、看護師がその専門性を活かしてどのように社会に貢献できるのかを考えていきましょう。従来の病院中心のイメージを超えて、看護師の社会貢献は多様な形で広がっています。
1. 医療機関での直接的なケア提供
最も伝統的な形ですが、病院や診療所などの医療機関で患者さんに直接ケアを提供することが、看護師の基本的な社会貢献です。
具体例:
- 急性期病院での救命救急や手術後の患者さんのケア
- 慢性期病院でのリハビリテーション支援や長期療養患者のケア
- 診療所での外来患者さんへの処置や健康指導
2. 地域における健康支援
高齢化社会の進展に伴い、地域で生活する人々の健康を支える看護師の役割が重要になっています。
具体例:
- 訪問看護師として在宅療養者の生活を支援
- 地域包括支援センターでの高齢者の健康相談や介護予防活動
- 保健師として地域全体の健康増進や感染症予防活動
- 産業看護師として職場の健康管理や労働衛生活動
3. 健康教育と予防医療
病気になってからの対応だけでなく、予防的な関わりや健康教育も看護師の重要な社会貢献です。
具体例:
- 学校看護師として子どもたちの健康教育や心身のケア
- 生活習慣病予防のための健康教室の開催
- 母子保健活動での妊産婦や乳幼児の健康支援
- 感染症対策の啓発や予防接種の推進
4. 災害時の医療支援
災害時における看護師の役割も重要な社会貢献の一つです。
具体例:
- 災害急性期の救護活動や応急処置
- 避難所での健康管理や感染症予防
- 被災者の心のケアやPTSD対策
- 災害弱者(高齢者・障害者・乳幼児など)への特別なケア
5. グローバルヘルスへの貢献
国境を越えた健康課題にも、看護師は貢献することができます。
具体例:
- 国際協力機構(JICA)などを通じた途上国への医療支援
- 難民キャンプでの医療ボランティア
- 国際的な感染症対策への参加
- グローバルヘルスに関する研究や政策提言
6. 看護教育と研究
次世代の看護師を育てることや、よりよいケアを追求するための研究も、重要な社会貢献です。
具体例:
- 看護学校や大学での教育活動
- 臨床現場での後輩指導や実習生の教育
- 看護研究による新しいケア方法の開発
- エビデンスに基づく看護実践の普及
7. 医療政策への参画
より大きな社会システムのレベルでも、看護師はその専門性を活かして貢献することができます。
具体例:
- 行政機関での医療政策の立案や評価
- 医療安全や感染管理などの専門的立場からの提言
- 看護師の労働環境改善のための活動
- 医療資源の適正配分や医療アクセスの公平性への取り組み
小論文で表現する「看護の専門性と社会貢献」
このテーマが小論文で出題された場合、どのように論じればよいでしょうか。以下に、小論文作成のポイントをいくつか紹介します。
1. 具体性を持たせる
抽象的な表現だけにとどまらず、具体的な例や場面を挙げることで説得力が増します。
抽象的な表現: 「看護師は患者の生活全体を見る専門職である」
具体性を持たせた表現: 「看護師は、患者さんの疾患だけでなく、例えば独居の高齢糖尿病患者さんであれば、自己注射が可能かどうか、栄養バランスの取れた食事の準備ができるか、低血糖時の対応ができるかなど、生活全体を視野に入れたケアを提供する専門職である」
2. 自分自身の考えや体験を織り交ぜる
教科書的な説明だけでなく、なぜあなたがそう考えるのか、どのような体験からその考えに至ったのかを述べることで、説得力と個性が生まれます。
例文: 「私が看護の専門性として特に重要だと考えるのは、患者さんの代弁者としての役割である。この考えに至ったのは、祖父が入院した際、認知症のために自分の思いを十分に表現できない祖父の小さなサインを読み取り、適切なケアにつなげてくれた看護師の姿に感銘を受けたからだ」
3. 多角的な視点から論じる
看護の専門性や社会貢献について、一面的ではなく多角的に論じることで、深い理解を示すことができます。
例文: 「看護師の社会貢献は、直接的なケア提供という側面だけでなく、予防的・教育的側面、研究・政策的側面など、多層的に捉えることができる。例えば、糖尿病患者のケアでは、適切な治療をサポートするだけでなく、セルフケア能力を高める教育的関わり、さらには糖尿病予防のための地域活動など、様々なレベルでの貢献が可能である」
4. 現代社会の課題と結びつける
現代社会が直面している健康課題や医療課題と看護の専門性を結びつけることで、社会的意義を強調できます。
例文: 「高齢化と人口減少が進む日本社会において、医療機関中心のケアから地域・在宅中心のケアへのシフトが求められている。このような社会変化の中で、看護師には医療と生活をつなぐ専門職として、地域で暮らす人々の健康を支援する新たな役割が期待されている」
5. 将来展望を示す
現状分析だけでなく、将来の看護や医療がどうあるべきか、自分はどのように貢献したいかという展望を示すことも重要です。
例文: 「今後の超高齢社会においては、治療を中心とした医療から予防と共生を重視した医療へのパラダイムシフトが必要である。私は看護師として、病気の治療だけでなく、人々が自分らしく健康に生きるための伴走者となり、一人ひとりの健康の社会的決定要因にも目を向けた包括的な支援を提供したい」
実践演習:看護の専門性と社会貢献に関する小論文を書いてみよう
以下のテーマで小論文を書く練習をしてみましょう。
テーマ:「看護の専門性とは何か、またその専門性を活かして社会にどのように貢献したいと考えるか、あなたの考えを600字程度で述べなさい。」
解答例:
看護の専門性とは、医学的知識と人間理解を統合し、生活者としての人間全体に焦点を当てたケアを提供することにあると考える。医師が主に疾患に焦点を当てるのに対し、看護師は病を持つ人の身体的側面だけでなく、精神的・社会的側面も含めた全人的ケアを行う。また、24時間継続して患者に関わることで見えてくる微細な変化を捉え、予防的視点も持ちながら「生きる」を支援するのが看護の本質である。 例えば、脳卒中後の高齢患者の場合、単に麻痺や言語障害などの症状管理だけでなく、その人の生活史や価値観を尊重しながら、残存機能を活かした生活再建を支援する。また、自分の思いを十分に表現できない患者の代弁者(アドボケイト)となり、その人らしさを守るのも看護師の重要な専門性である。 この専門性を活かした社会貢献として、私は特に地域における予防的健康支援に関心がある。現代社会では、超高齢化と疾病構造の変化により、病院完結型の医療から地域完結型の医療への転換が求められている。この変化の中で、看護師には医療と生活をつなぐ架け橋としての役割が期待されている。 私自身は、将来的に訪問看護師として在宅療養者を支援したいと考えている。祖父の在宅療養を支えた訪問看護師の姿に感銘を受けたことがきっかけだ。専門的な医療処置だけでなく、その人の生活環境を整え、家族も含めたケアを提供することで、住み慣れた地域で自分らしく生きることを支援したい。 また、地域の健康教室などを通じて予防的な健康支援にも取り組みたい。生活習慣病や認知症などは早期からの予防が重要であり、看護の専門的知識を活かした健康教育により、地域全体の健康増進に貢献できると考えている。「治す医療」と「支える医療」の両面から、人々のQOL向上に寄与する看護師を目指したい。
ポイント解説:
- 冒頭で看護の専門性について明確に定義しています
- 具体的な例(脳卒中後の高齢患者)を挙げて説明しています
- 自分が特に関心を持つ社会貢献の形(地域における予防的健康支援)を示しています
- 個人的な体験(祖父と訪問看護師)を織り交ぜて説得力を高めています
- 現代社会の課題(超高齢化と医療の変化)と結びつけて論じています
- 具体的な将来ビジョン(訪問看護師、健康教室の開催)を示しています
まとめと次回予告
今回は「看護の専門性と社会貢献」について解説しました。看護の専門性とは、生活者の視点でのケア、「生きる」を支える実践知、予防的視点と健康増進、継続的な関わりと変化の見守り、代弁者としての役割など、多面的に捉えることができます。また、その専門性を活かした社会貢献の形も、医療機関での直接的なケア提供から、地域における健康支援、健康教育と予防医療、災害時の医療支援、グローバルヘルスへの貢献、看護教育と研究、医療政策への参画まで、多様に広がっています。
看護学科の入試で「看護の専門性と社会貢献」について問われた際には、具体的な例を挙げながら、自分自身の考えや体験を織り交ぜ、多角的な視点から論じることが大切です。また、現代社会の課題と結びつけ、将来展望を示すことで、より説得力のある小論文になるでしょう。
次回は「自己の経験を看護に結びつける」について解説します。自分の経験や体験をどのように看護と結びつけて表現するか、説得力のある小論文を書くためのコツを詳しく学んでいきましょう。
皆さんの小論文学習が実り多きものになることを願っています!