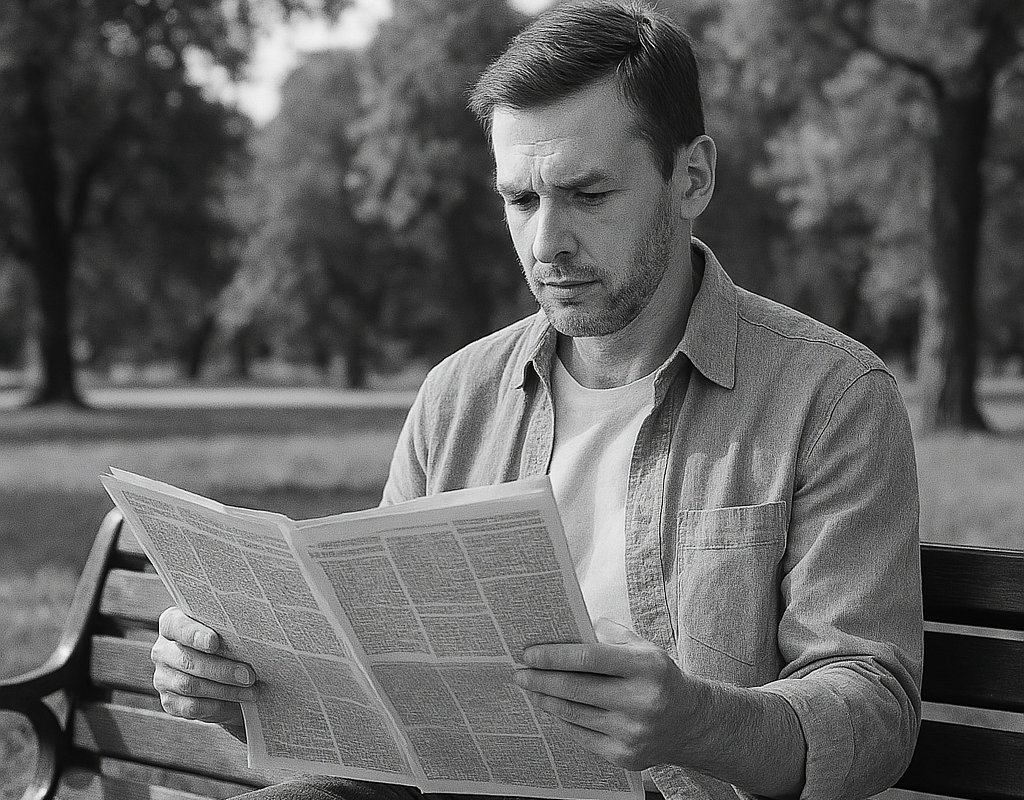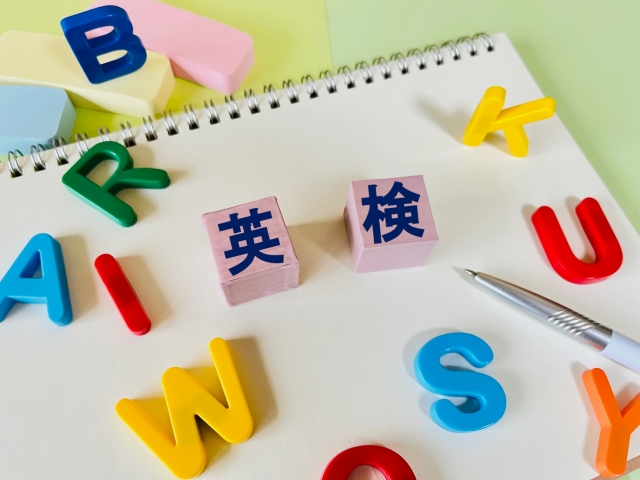はじめに
こんにちは、英語学習者のみなさん!いよいよ英検準2級対策シリーズの最終回となりました。前回は「メール文の共通間違いと添削のコツ」について学びました。今回は「本番で使える!時間配分と最終チェックリスト」というテーマで、試験直前の練習法と本番での時間管理術について詳しく解説します。
いくら英作文の書き方を学んでも、試験本番で時間が足りなければ力を発揮できません。また、焦りから避けられるミスをしてしまうこともあります。この記事では、限られた時間内で最大限の力を発揮するためのコツと、最終チェックのポイントを紹介します。
これまでの9回の内容をしっかり復習して、自信を持って試験に臨みましょう!
英検準2級ライティングの基本情報の確認
まずは、英検準2級のライティング問題の基本情報を確認しておきましょう。
出題形式
- 従来の意見文:与えられたテーマについて自分の意見を50-60語程度で書く
- 新形式メール文:外国人の知り合いからのメールに対して40-50語程度で返信を書く
試験時間
- ライティングを含む筆記試験全体で75分
- ライティングには約15-20分を使うのが理想的
配点と評価ポイント
- ライティングは筆記試験全体の約20%の配点
- 内容、語彙、文法、スペル、語数、フォーマットなどが評価される
- メール文では特に、質問を2つ含めることと相手の質問に答えることが重要
試験本番での効果的な時間配分
限られた時間内で両方の英作文をしっかり書くためには、計画的な時間配分が重要です。以下に理想的な時間配分を紹介します。
意見文(従来形式)の時間配分:約8-10分
- 問題文の理解:1分
- テーマをしっかり読み、何について書くべきかを正確に理解する
- 構想・メモ作り:2分
- 自分の意見(賛成・反対)を決める
- 理由を2つ程度考える
- 簡単な構成をメモする(導入→意見→理由→結論)
- 英文作成:4-5分
- メモに基づいて実際に英文を書く
- 語数をカウントしながら進める
- 見直し:1-2分
- スペル、文法、語数などを確認
- 特に時制や主語と動詞の一致をチェック
メール文(新形式)の時間配分:約7-8分
- 問題文の理解:1分
- 相手のメールを読み、内容と質問を正確に理解する
- 下線部を特に注意して確認する
- 構想・メモ作り:1-2分
- 相手の質問への回答を考える
- 下線部に関する質問を2つ考える
- メールの簡単な構成を決める
- 英文作成:3-4分
- メモに基づいて実際に英文を書く
- 語数をカウントしながら進める
- 見直し:1分
- スペル、文法、語数などを確認
- 質問が2つ含まれているか確認
- 相手の質問に答えているか確認
残りの時間の使い方
筆記試験全体の中で、リーディングやリスニングの問題が終わった後に時間が余った場合は、ライティングの見直しに使うと良いでしょう。特に以下の点を再確認してください:
- スペルミスや文法エラー
- 語数制限を守れているか
- 内容が問題の要求に合っているか
本番前の効果的な練習方法
試験本番で実力を発揮するためには、事前の練習がとても重要です。以下に効果的な練習方法を紹介します。
1. 時間を測って練習する
実際の試験と同じ時間設定で練習することで、時間感覚が身につきます。
毎回、時間を測って書く練習をすることで、本番でも焦らずに書けるようになります。
2. 過去問や模擬問題を活用する
英検準2級の過去問や市販の模擬問題集を使って練習しましょう。実際の試験と同じ形式の問題に取り組むことで、出題傾向に慣れることができます。
3. 模範解答と比較する
自分の書いた英作文と模範解答を比較し、以下の点を分析しましょう:
- 語彙や表現の選び方
- 文の構造や長さ
- 全体の構成や流れ
- 時間内に書ける文章量
4. 弱点を集中的に強化する
練習を通じて見つかった弱点を集中的に強化しましょう:
- 特定の文法項目が苦手なら、その練習問題を解く
- 語彙力に不安があれば、頻出語彙を復習する
- 時間内に書けない場合は、簡潔な表現を学ぶ
5. カウントダウン形式で練習する
試験終了の5分前、3分前、1分前という状況を想定して、残り時間に応じた対処法を練習しておくと良いでしょう。
- 残り5分:英作文を書き終え、見直しを始める
- 残り3分:重要なポイント(質問2つ、相手の質問への回答など)を確認
- 残り1分:語数の最終確認と簡単なスペルチェック
試験本番のための最終チェックリスト
試験本番で見落としがないように、以下のチェックリストを活用しましょう。
意見文(従来形式)のチェックリスト
内容面
- [ ] テーマに沿った内容になっているか
- [ ] 自分の意見が明確に述べられているか
- [ ] 理由や例が適切に示されているか
- [ ] 論理的な流れになっているか
構成面
- [ ] 導入部で話題と自分の立場を示しているか
- [ ] 本文で理由や例を挙げているか
- [ ] 結論部で意見をまとめているか
言語面
- [ ] 語数は50-60語程度か
- [ ] 文法(時制、主語と動詞の一致など)は正確か
- [ ] スペルミスはないか
- [ ] 句読点は適切か
メール文(新形式)のチェックリスト
内容面
- [ ] 相手のメールに対して適切に応答しているか
- [ ] 下線部に関する質問を2つ含めているか
- [ ] 相手の質問に答えているか
- [ ] 友人間のカジュアルなトーンになっているか
構成面
- [ ] 挨拶で始まっているか(すでに記載されている部分)
- [ ] 本文で必要な情報と質問を含めているか
- [ ] 結びの言葉で終わっているか(可能であれば)
言語面
- [ ] 語数は40-50語程度か
- [ ] 文法(時制、主語と動詞の一致など)は正確か
- [ ] スペルミスはないか
- [ ] 句読点は適切か
前回の練習問題解答例
前回の練習問題「間違いを含む英文の修正」の解答例:
間違いのある原文:
Hi, Alex!
Thank you for you’re e-mail.
I happy to hear about your new job. It sound very interesting! I never worked in a restaurant before, but I think it must be excited. How many hour do you work per week? What kind of foods does the restaurant serves? I have busy with my studies lately, so I not have much free time.
Best wishes,
修正した文:
Hi, Alex!
Thank you for your e-mail.
I’m happy to hear about your new job. It sounds very interesting! I’ve never worked in a restaurant before, but I think it must be exciting. How many hours do you work per week? What kind of food does the restaurant serve? I’ve been busy with my studies lately, so I don’t have much free time.
Best wishes,
修正ポイント:
- you’re → your(所有格)
- I happy → I’m happy(be動詞の追加)
- It sound → It sounds(三人称単数の-s)
- I never worked → I’ve never worked(現在完了形)
- excited → exciting(感情を表す形容詞と対象を表す形容詞の区別)
- hour → hours(複数形)
- foods → food(不可算名詞)
- does…serves → does…serve(助動詞のあとは原形)
- I have busy → I’ve been busy(現在完了進行形)
- I not have → I don’t have(否定形)
試験当日の心構えとコツ
1. 十分な睡眠と食事を取る
試験前日は十分な睡眠を取り、当日は栄養のある食事を摂りましょう。体調を整えることで、集中力が高まります。
2. 時間に余裕を持って会場に向かう
試験会場には余裕を持って到着し、落ち着いた状態で試験に臨めるようにしましょう。
3. 試験中の集中力を維持する
- 深呼吸をして緊張を和らげる
- 他の受験者と比べず、自分のペースを守る
- 途中で行き詰まったら、次の問題に進む
4. 試験中にミスをしても慌てない
ミスをしたと感じても、慌てずに冷静に対応しましょう。修正できるものは修正し、できないものは次に進みます。完璧を求めすぎないことが大切です。
5. 残り時間を常に意識する
定期的に残り時間を確認し、計画通りに進められているか確認しましょう。もし時間が足りなくなりそうなら、簡潔な表現を心がけて調整します。
全10回のシリーズの総まとめ
最後に、全10回にわたって学んだ内容を簡単に振り返ってみましょう。
- 英検準2級新形式メール文の基本と特徴:新形式の出題傾向と従来の意見文との違い
- メール文の基本フォーマットとマナー:英文メールの書式、挨拶表現、丁寧さの調整法
- 目的別メール文の書き方①:依頼・お願い:効果的な依頼表現と理由の説明方法
- 目的別メール文の書き方②:お礼・感謝:感謝の気持ちを伝える様々な表現と例文
- 目的別メール文の書き方③:招待・案内:イベントや活動への招待表現と情報提示法
- メール文で効果的に使える接続表現:文や段落をスムーズにつなぐテクニック
- 状況別メール文対策①:学校生活・イベント:学校関連の場面で使える表現と例文
- 状況別メール文対策②:日常生活・旅行:日常や旅行に関する表現と体験の伝え方
- メール文の共通間違いと添削のコツ:よくある間違いと自己添削のテクニック
- 本番で使える!時間配分と最終チェックリスト:試験直前の練習法と本番での時間管理術
これらの内容をしっかり復習し、実践することで、英検準2級の新形式メール文に自信を持って取り組めるようになるでしょう。
最後に
英検準2級対策シリーズはこれで終了となりますが、学んだことを継続的に練習し、実際のコミュニケーションでも使えるようにしていただければ嬉しいです。
英語学習は一朝一夕では完成しません。継続的な学習と実践を通じて、少しずつでも確実に力をつけていきましょう。皆さんの英検準2級合格を心より応援しています!
がんばってください!