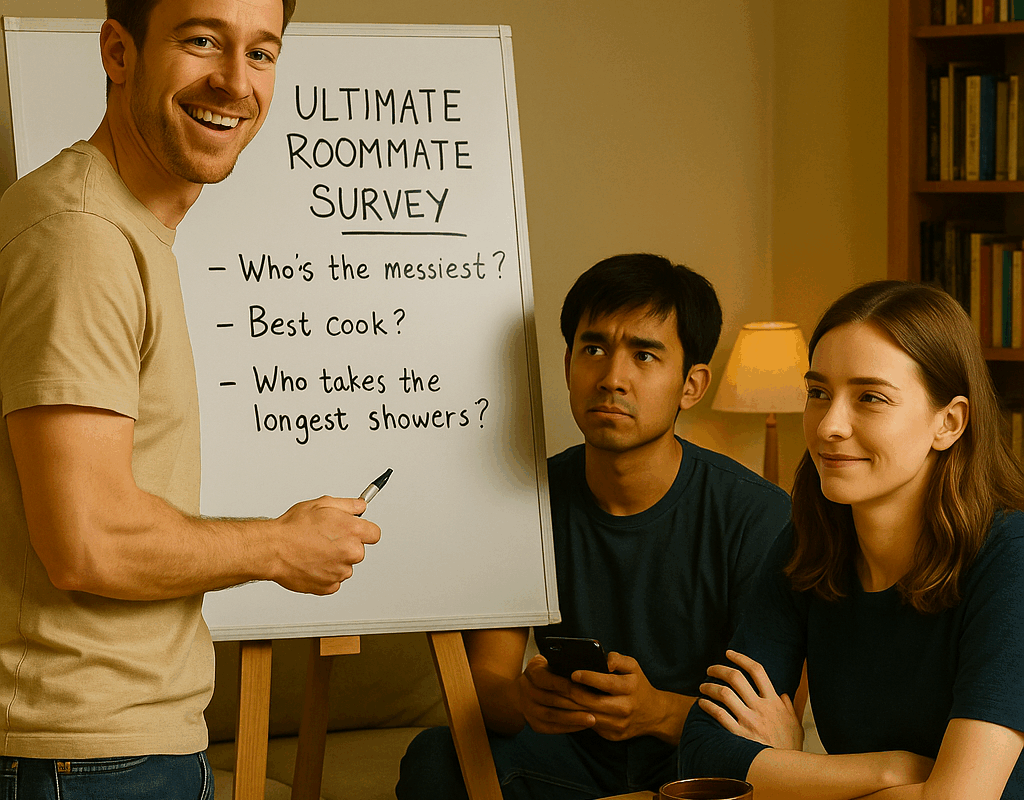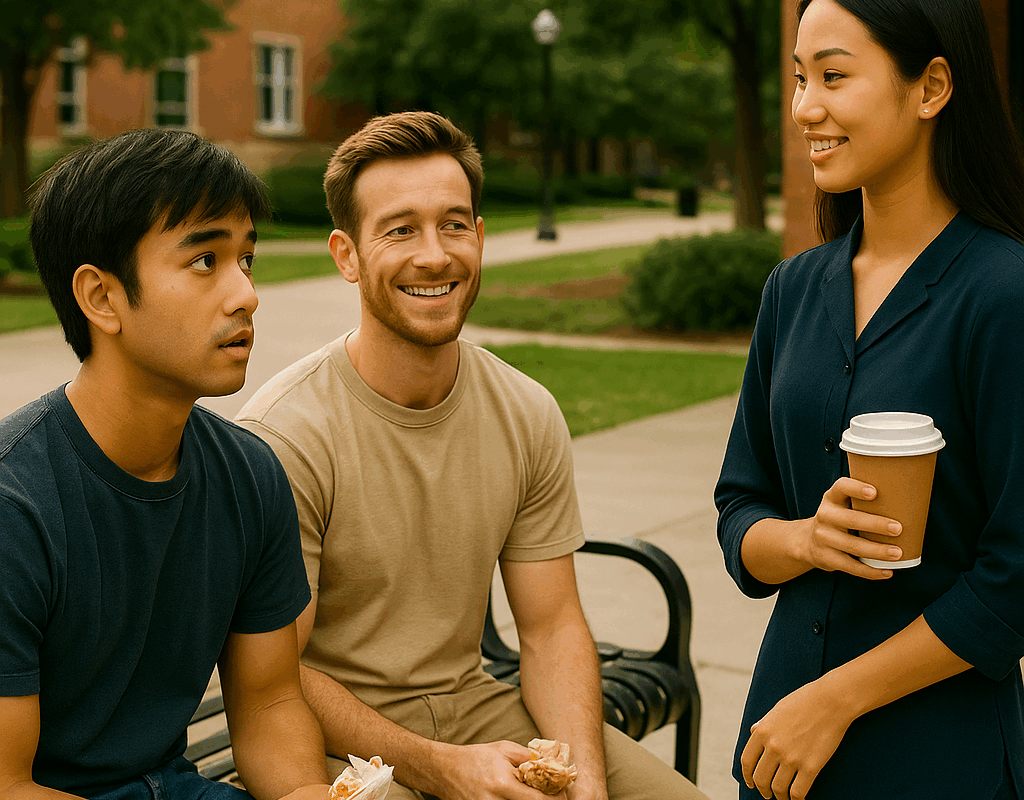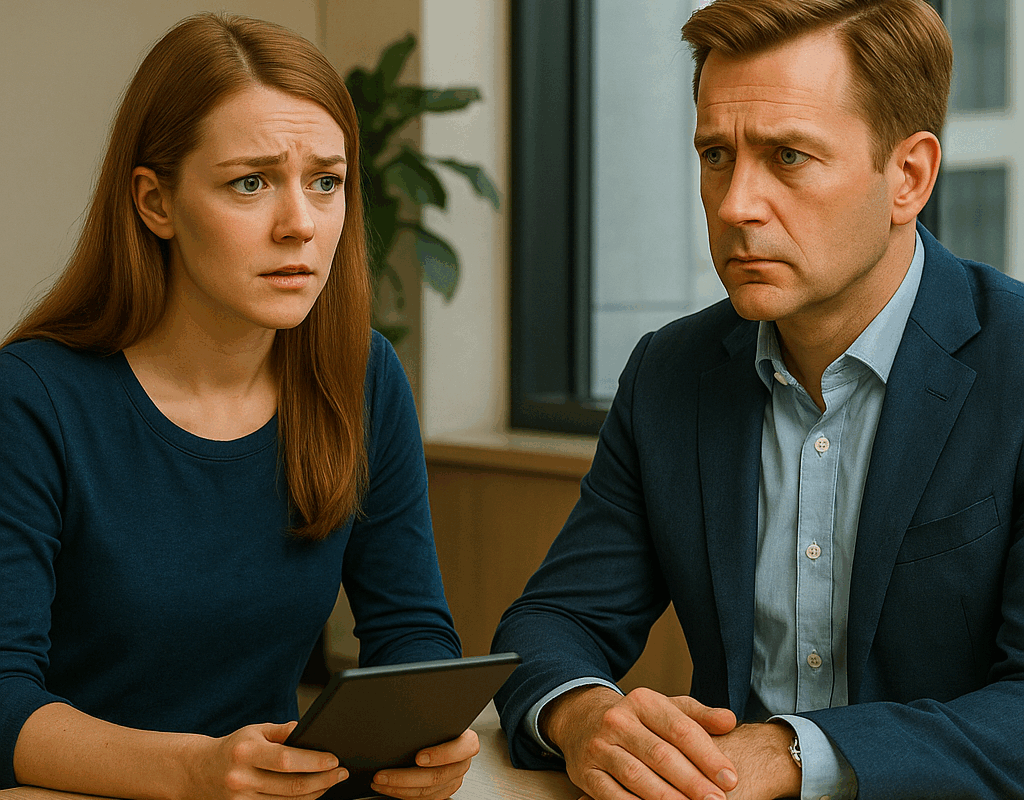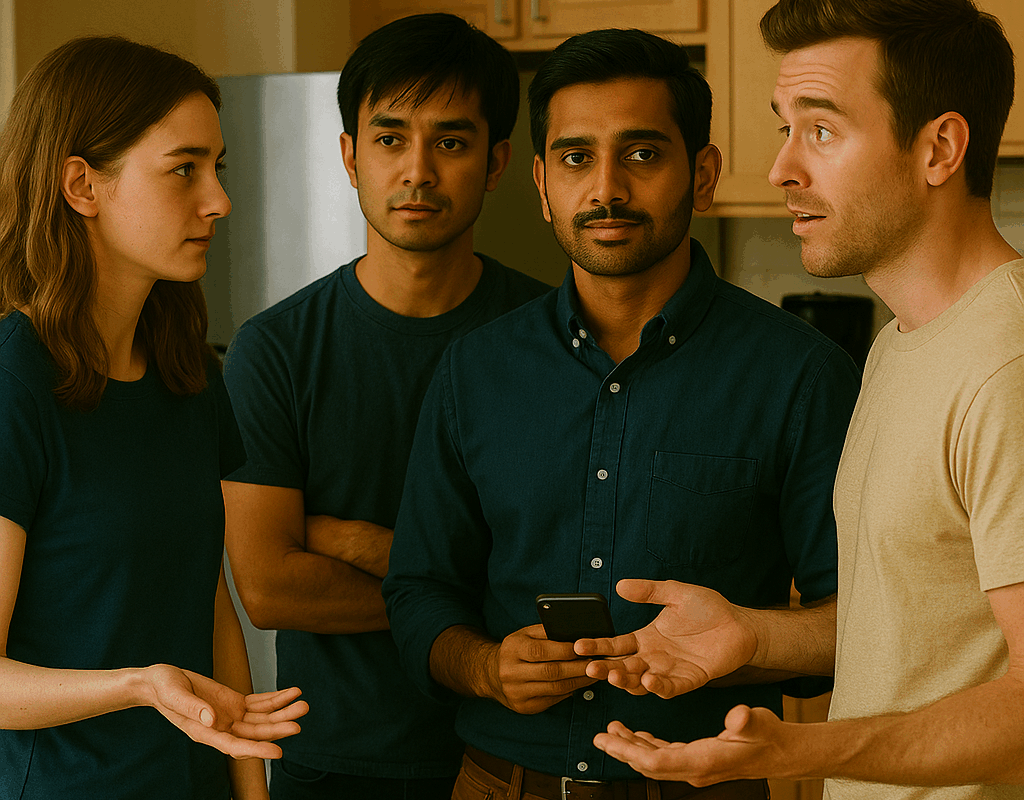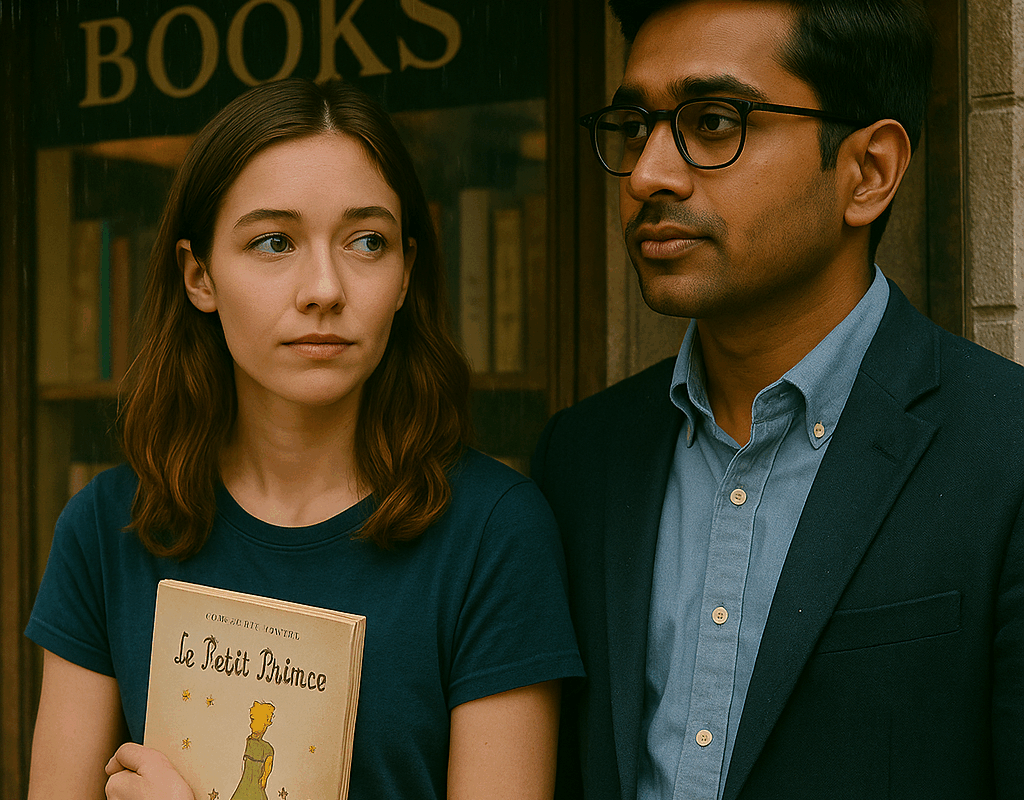🎬 Scene
今日の舞台は、いつものMaple Houseの共有スペース。
Donnyが突然始めたのは、「ルームメイト・ランキング・アンケート」!?
「一番夜更かししてる人は?」「料理が一番上手い人は?」…という質問に、Margotは余裕のリアクション。
一方、Taroはどこか落ち着かない様子で…?
💡 会話を聞いてみましょう!
📌 登場人物
Donny:明るくフレンドリーな学生。思ったことはすぐ口に出すタイプ。
Taro(日本出身・実直だがおっとり気味の交換留学生)
Magot(オーストラリア出身・文学好きの学生、几帳面でまじめ、ルールを守りたい派)
◆ 会話スクリプト(英語+和訳)
[Scene opens with Donny setting up a whiteboard in the living room. Toro is on the couch scrolling his phone. Margot is sipping tea at the table.]
Donny :
Alright, people! Today’s topic: “The Ultimate Roommate Survey!”
(さあ皆さん!今日のテーマは『究極のルームメイトアンケート』!)
Taro :
Wait, what?
(は?何それ?)
Donny :
Anonymous voting. Questions like: “Who’s the messiest?”, “Who’s the best cook?”, “Who takes the longest showers?”
(匿名投票でやるんだ。“一番部屋が汚い人”とか、“一番料理が上手な人”とか、“シャワーが一番長い人”とかね。)
Margot :
Sounds like a trap.
(それ、罠でしょ。)
Donny:
No way! It’s just for fun. Totally anonymous. Zero consequences!
(そんなわけないって!ただの遊び。完全匿名。何の影響もなし!)
Taro :
Says the guy who once posted a pie chart of fridge ownership percentages.
(冷蔵庫の所有割合を円グラフで公開したやつの言うことか。)
Donny :
Hey, data is power, my friend.
[Cut to later. Donny is reading results aloud from a stack of anonymous slips.]
Donny :
According to the survey… Margot is voted “Best Cook”!
(アンケートによると… マーゴが“料理が一番上手”に選ばれました!)
Taro :
Who wrote that? Was it anonymous?
(誰が書いたんだよ?匿名ってほんとか?)
Margot :
Taro, relax. It’s not a court trial.
(太郎、落ち着いて。これは裁判じゃないのよ。)
Donny:
Also… “Noisiest Roommate”… is a tie between Taro and Donny.
(そして…“一番うるさいルームメイト”…は、トロとドニーで同票だってさ。)
Taro:
What?! I’m quieter than a mouse.
(はぁ!?俺はネズミより静かだぞ。)
Margot (deadpan):
Maybe a mouse with steel-toed boots.
(たぶんスチール入りブーツを履いたネズミね。)
Donny (laughs, holding up last result):
Final category—“Most Mysterious Roommate”… goes to Margot.
(最後のカテゴリ—“一番ミステリアスなルームメイト”…はマーゴに決定!)
Margot (smiling slightly):
I’ll take that as a compliment.
(それは褒め言葉として受け取っておくわ。)
[Everyone chuckles. The awkwardness melts into laughter.]
Donny:
See? Surveys bring people together!
(ね?アンケートって人をつなぐでしょ!)
Taro:
Until someone creates a “Who left the dishes” poll…
(誰かが“誰が皿を放置したか”アンケートを作るまではな。)
Margot:
That’s when war begins.
(それが戦争の始まりね。)
[Scene fades out with everyone laughing and Margot topping off her tea.]
🗨️ Highlighted Lines
Donny: “According to the survey, someone thinks Margot is the best cook!”
Toro: “Who wrote that? Was it anonymous?”
Margot: “Taro, relax. It’s not a court trial.” 😏
💡 Vocabulary & Phrases
- According to the survey:調査によると
- Turns out that…:~ということがわかった
- Who’s the noisiest roommate?:誰が一番うるさいルームメイト?
- If I had to guess…:あえて言うなら…(仮定法)
🧑💼 Margot’s One-Liner
“Surveys are fun… until you realize who voted for you.”
(アンケートって楽しいよね…自分に票を入れた人が誰か気づくまでは。)
友情、ユーモア、そしてちょっとの緊張感——Eastfieldの生活は今日もにぎやかです!
次回もお楽しみに!